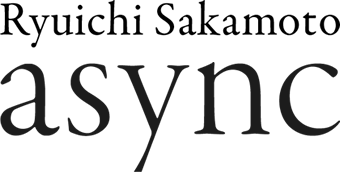予習 『左うでの夢』(1981年作品)と“B-2 Units”
坂本龍一の3作目のソロ・アルバムが1981年に発表された『左うでの夢』。ミニマルかつアヴァンギャルドなテクノ・アルバムである前作『B-2 Unit』に対して、1年後のこのアルバムは。前作の反動のように即興や肉体性を重視したアルバムとなった。
『B-2 Unit』がポップ・バンドであった当時のYMOへの一種の反動として生まれたアンチ・ポップなアルバムであったのと同様、この作品もまた、シーケンサーとコンピューターと同期したYMOにはできない音楽をやろうという意思があり、やはりYMOへの反動が見てとれる。
フランク・ザッパやデヴィッド・ボウイ、トーキング・ヘッズとの共演で知られていた、まさに即興的な演奏を得意とする米人ギタリストのエイドリアン・ブリュー、EP-4の佐藤薫らというレコーディング・メンバーの人選を見てもそれは明らかだ。
しかし、このアルバムの、坂本龍一の歴史の上でもっともユニークなのはレコーディングに招いたロビン・スコットの存在だろう。
ロビン・スコットはユニット“M”の名義で知られる英国のアーティストで、世界的なディスコ・ヒットとなったテクノ・ポップ曲「ポップ・ミューヂック」(1979)で知られる。が、このスコットはそうしたダンス・ミュージックのみならずアフリカの民族音楽などにも造詣の深い才人で、坂本龍一がアルバムに招こうと思ったのもそうした多面性を評価したからであろうことは想像に難くない。
しかし、問題はこの『左うでの夢』のレコーディングが進む間、坂本龍一とロビン・スコットは、それぞれいまやっているレコーディングは相手(坂本龍一にとってはロビン・スコット、ロビン・スコットにとっては坂本龍一)をコラボレーターとした自分のソロ・アルバム、もしくはロビン・スコットにはふたりの共同名義のユニットのアルバムであるという意識があり、レコーディングのリーダー・シップが曖昧になってしまったこと。
最終的には坂本龍一のソロ・アルバムである本作と、ロビン・スコット主導のミニ・アルバム『ジ・アレンジメント』ならびに両者のコレボレーション・シングルという形で欧米において発売された「ワンス・イン・ア・ライフ・タイム」というセパレートな形に落ち着くことにはなったが、双方にとって、ちょっと曖昧で不満の残る結果にはなってしまった。
ただし、坂本龍一にとっては、この『左うでの夢』を契機に、YMOとはちがう即興性を重視した生バンドをやろうという、自身初のリーダー・バンドを結成する動機になったことは大きい。
そのソロ・バンドが『左うでの夢』のレコーディング・メンバーである管楽器奏者のロビン・トンプソン、ギター、サックスの立花ハジメに、ベースの永田純、ドラムスの鈴木さえ子、サックスの沢村満による“B-2 Units”。『左うでの夢』の楽曲を演奏できるバンドということで、バンド名案には当初“龍ちゃんズ”なども挙がっていたが、結局はこの“B-2 Units”に落ち着いた(“B-2 Units”ではあるがアルバム『B-2 Unit』からは「ザットネス・アンド・ゼアネス」しか演奏しないという結果とはなったが…)。
この“B-2 Units”は1981年から1982年にかけて日本各地でのコンサートや、NHKでの公開録音などで活発に活動した。バンドのためのオリジナル曲や、坂本龍一と立花ハジメのソロ曲、YMOの曲などもレパートリーに入り、リスナーやファンからの評価も高かった。しかし、やがて“B-2 Units”は立花ハジメのバック・バンドと有為転変し、坂本龍一はバンド・リーダーからいちメンバーに転落していくという物語は、この“B-2 Units”の当時の演奏5曲を収録したコンピレーション『Year Book 1980-1984』のブックレットに記載の坂本龍一自身の涙のインタビュー・コメントを参照されたい。
ともあれ、これまで録音物がなかったために、ライヴを実際に目にし、ラジオで耳にできたファン以外にはその実態がいまひとつ不明だった“B-2 Units”のおもしろさ、充実が記録された『Year Book 1980-1984』は、最新作『async』と同日にリリースされる。
そこになんらかの相関があるのかどうか、ぜひ確かめてみてほしい。
(執筆:吉村栄一)
『B-2 Unit』がポップ・バンドであった当時のYMOへの一種の反動として生まれたアンチ・ポップなアルバムであったのと同様、この作品もまた、シーケンサーとコンピューターと同期したYMOにはできない音楽をやろうという意思があり、やはりYMOへの反動が見てとれる。
フランク・ザッパやデヴィッド・ボウイ、トーキング・ヘッズとの共演で知られていた、まさに即興的な演奏を得意とする米人ギタリストのエイドリアン・ブリュー、EP-4の佐藤薫らというレコーディング・メンバーの人選を見てもそれは明らかだ。
しかし、このアルバムの、坂本龍一の歴史の上でもっともユニークなのはレコーディングに招いたロビン・スコットの存在だろう。
ロビン・スコットはユニット“M”の名義で知られる英国のアーティストで、世界的なディスコ・ヒットとなったテクノ・ポップ曲「ポップ・ミューヂック」(1979)で知られる。が、このスコットはそうしたダンス・ミュージックのみならずアフリカの民族音楽などにも造詣の深い才人で、坂本龍一がアルバムに招こうと思ったのもそうした多面性を評価したからであろうことは想像に難くない。
しかし、問題はこの『左うでの夢』のレコーディングが進む間、坂本龍一とロビン・スコットは、それぞれいまやっているレコーディングは相手(坂本龍一にとってはロビン・スコット、ロビン・スコットにとっては坂本龍一)をコラボレーターとした自分のソロ・アルバム、もしくはロビン・スコットにはふたりの共同名義のユニットのアルバムであるという意識があり、レコーディングのリーダー・シップが曖昧になってしまったこと。
最終的には坂本龍一のソロ・アルバムである本作と、ロビン・スコット主導のミニ・アルバム『ジ・アレンジメント』ならびに両者のコレボレーション・シングルという形で欧米において発売された「ワンス・イン・ア・ライフ・タイム」というセパレートな形に落ち着くことにはなったが、双方にとって、ちょっと曖昧で不満の残る結果にはなってしまった。
ただし、坂本龍一にとっては、この『左うでの夢』を契機に、YMOとはちがう即興性を重視した生バンドをやろうという、自身初のリーダー・バンドを結成する動機になったことは大きい。
そのソロ・バンドが『左うでの夢』のレコーディング・メンバーである管楽器奏者のロビン・トンプソン、ギター、サックスの立花ハジメに、ベースの永田純、ドラムスの鈴木さえ子、サックスの沢村満による“B-2 Units”。『左うでの夢』の楽曲を演奏できるバンドということで、バンド名案には当初“龍ちゃんズ”なども挙がっていたが、結局はこの“B-2 Units”に落ち着いた(“B-2 Units”ではあるがアルバム『B-2 Unit』からは「ザットネス・アンド・ゼアネス」しか演奏しないという結果とはなったが…)。
この“B-2 Units”は1981年から1982年にかけて日本各地でのコンサートや、NHKでの公開録音などで活発に活動した。バンドのためのオリジナル曲や、坂本龍一と立花ハジメのソロ曲、YMOの曲などもレパートリーに入り、リスナーやファンからの評価も高かった。しかし、やがて“B-2 Units”は立花ハジメのバック・バンドと有為転変し、坂本龍一はバンド・リーダーからいちメンバーに転落していくという物語は、この“B-2 Units”の当時の演奏5曲を収録したコンピレーション『Year Book 1980-1984』のブックレットに記載の坂本龍一自身の涙のインタビュー・コメントを参照されたい。
ともあれ、これまで録音物がなかったために、ライヴを実際に目にし、ラジオで耳にできたファン以外にはその実態がいまひとつ不明だった“B-2 Units”のおもしろさ、充実が記録された『Year Book 1980-1984』は、最新作『async』と同日にリリースされる。
そこになんらかの相関があるのかどうか、ぜひ確かめてみてほしい。
(執筆:吉村栄一)